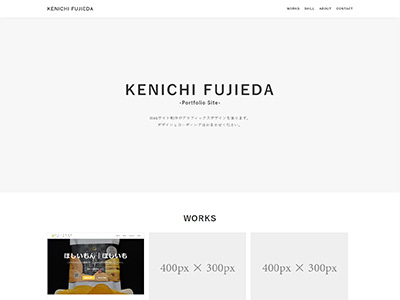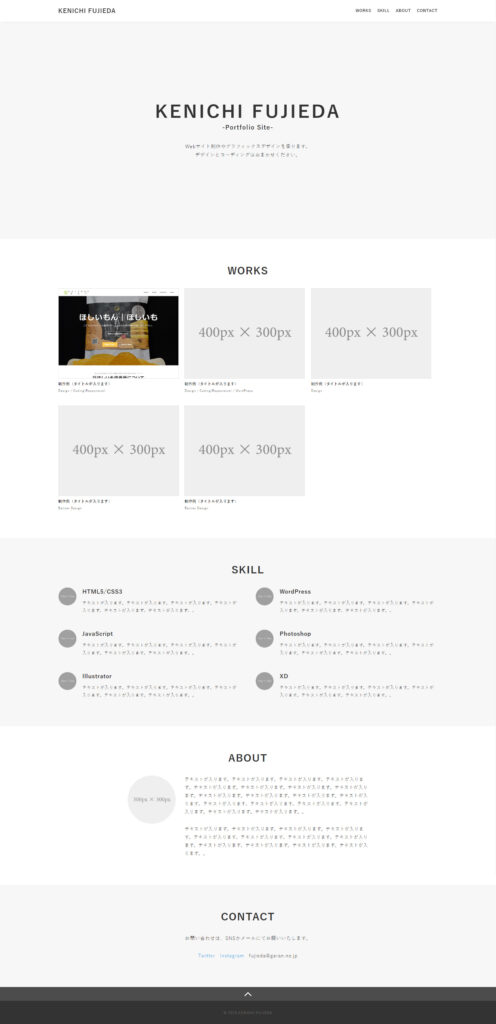WordPressのマルチサイト化の設定方法について、この記事では詳しく説明します。マルチサイトとは、一つのWordPressインストールで複数のサイトを運用できる機能のことです。マルチサイトを利用すると、サイトの管理が簡単になりますし、プラグインやテーマの共有もできます。しかし、マルチサイト化には注意点もあります。例えば、サブドメインやサブディレクトリの設定が必要ですし、サーバーの負荷が高くなる可能性もあります。そこで、マルチサイト化をする前に、以下のステップを踏んでください。
- マルチサイト化の必要性を確認する
- マルチサイト化に対応したホスティングプランを選ぶ
- バックアップを取る
- wp-config.phpファイルを編集する
- ネットワーク管理画面にアクセスする
- サブドメインかサブディレクトリかを選ぶ
- ネットワーク設定を行う
- .htaccessファイルを編集する
- 新しいサイトを作成する
- プラグインやテーマを有効化する
以上が、WordPressのマルチサイト化の設定方法です。
この方法であれば、簡単に複数のサイトを一括管理できます。ただし、マルチサイト化は初心者には難しい場合もありますし、トラブルが発生する可能性もあります。そのため、マルチサイト化をする際には、十分に注意してください。
wp-config.phpを編集する
wp-config.phpは、WordPressをインストールしたディレクトリにあるファイルです。このファイルをFTPでダウンロードし、テキストエディタで開きます。
以下のコードをファイルの最後に追加します。
PHP
// マルチサイト化を許可する
define('WP_ALLOW_MULTISITE', true);
// ネットワーク名を設定
define('WP_NETWORK_NAME', 'Your Network Name');
コードは慎重に使用してください。
注意点
define()関数は、定数を定義する関数です。WP_ALLOW_MULTISITEとWP_NETWORK_NAMEは、マルチサイト化を許可するための定数です。
- WP_NETWORK_NAMEには、好きな名前を入力する
WP_NETWORK_NAMEには、ネットワークの名前を入力します。この名前は、ネットワーク内のすべてのサイトに表示されます。
ネットワークの設定を確認する
WordPressの管理画面にログインし、「ツール」→「サイトネットワークの設置」にアクセスします。
「マルチサイトのタイプ」で、サブディレクトリ型かサブドメイン型を選択します。
「サイトネットワーク名」は、wp-config.phpに設定したWP_NETWORK_NAMEと同じ名前を入力します。
「サブドメインを有効にする」にチェックを入れると、すべてのサブドメインをマルチサイトに追加できます。
ネットワークをインストールする
「ネットワークをインストールする」をクリックすると、マルチサイトのインストールが始まります。
インストールが完了すると、ネットワーク管理者のページが表示されます。
wp-config.phpに追記する
マルチサイトをインストールすると、wp-config.phpに以下のコードが追加されます。
PHP
// マルチサイト化を有効にする
if ( ! defined( 'WP_ALLOW_MULTISITE' ) ) {
define( 'WP_ALLOW_MULTISITE', true );
}
// ネットワーク名を設定
if ( ! defined( 'WP_NETWORK_NAME' ) ) {
define( 'WP_NETWORK_NAME', 'Your Network Name' );
}
// サブドメインを有効にする
if ( ! defined( 'SUBDOMAIN_INSTALL' ) ) {
define( 'SUBDOMAIN_INSTALL', true );
}
コードは慎重に使用してください。
htaccessに追記する
WordPressのインストールディレクトリにある.htaccessに以下のコードを追加します。
Apache
# マルチサイトを有効にする
RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteRule ^index\.php$ - [L]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule . index\.php [L]
コードは慎重に使用してください。
再度ログインする
WordPressの管理画面に再度ログインすると、ネットワーク管理者のページが表示されます。
サイトを追加する
「サイト」→「サイトの追加」にアクセスして、新しいサイトを追加します。
サイトのURL、管理者アカウント、サイトのタイトル、説明を入力します。
「サイトを追加する」をクリックすると、新しいサイトが追加されます。
これで、マルチサイトの設定は完了です。
注意点
- マルチサイト化は、既存のサイトに影響を与える可能性があるため、バックアップを作成してから行ってください。
- マルチサイトを利用する場合は、ネットワークのセキュリティ対策を強化してください。
マルチサイト化をすることで、以下のメリットがあります。
- 1つのWordPressで複数のサイトを作成・運用できる
- 複数のサイトの管理を効率化できる
- ネットワーク全体でプラグインやテーマを共有できる
- ネットワーク全体でユーザーを管理できる
ただし、以下のデメリットもあります。
- サーバーの負荷が大きくなる可能性がある
- セキュリティ対策が複雑になる可能性がある
- ネットワークの構成が複雑になる可能性がある